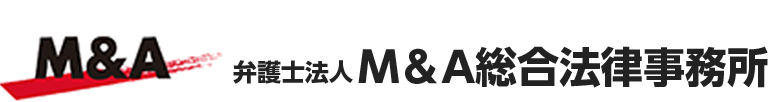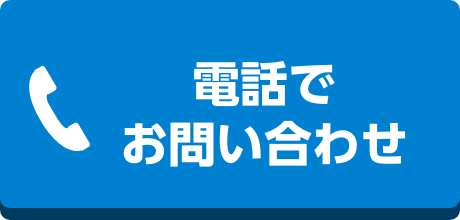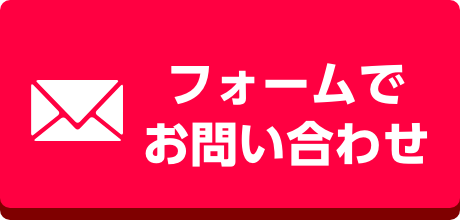相続人等に対する相続株式売渡請求(スクイーズアウト)手続きについて!

中小企業などの株主が亡くなった場合、一般的には被相続人が所有している株式は相続人へ相続されます。
しかし、会社側は、その相続人に株式を保有させたくないケースもあるかもしれません。
会社の株式を被相続人が保有していた時は、会社が承認している人物が株式を保有していたことになります。
一方、相続人が相続をして株式を保有する場合は、相続人が会社と関係が薄いことが多く株式を回収したいと考えるケースが多々あります。
この時に相続人から株式を買い取るための協議がうまくいけばいいのですが、協議がうまく成立しないこともよくあるのです。
このような場合、会社は、「相続人等に対する相続株式売渡請求(スクイーズアウト)手続き」という制度を利用することができます。
なお、スクイーズアウトとは、一般的に「一定の手続により少数株主から強制的に株式を取得し、会社または大株主が100%支配を実現するための総称」を意味し、相続人に対する売渡請求(会社法174条)はその一類型に当たります。
一般のスクイーズアウト手法としては、
- 特別支配株主による株式等売渡請求(会社法179条)
- 株式併合(1株未満整理)
- 全部取得条項付種類株式の活用
- 合併・株式交換等の組織再編手法
などが存在し、174条の売渡請求は「相続を契機として株式が意図しない者に承継されることを防ぐ」という目的に特化した制度です。
事業承継・中小企業のオーナー交代においては、相続による株式分散や、会社経営への理解がない相続人による意思決定の停滞を防ぐため、この174条手続は非常に重要な位置づけを持ちます。
今回は、相続人等に対する相続株式売渡請求手続き(スクイーズアウト)について詳しく解説していきます。
相続人等に対する相続株式売渡請求(スクイーズアウト)
相続人等に対する売渡請求とは、会社法174条で以下のように定義されています。
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求(スクイーズアウト)することができる旨を定款で定めることができる。
上記のとおり、相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の行使に関しては、会社法第174条に基づき行われます。この制度は、定款に売渡請求の規定を設けることで活用でき、相続その他の一般承継により取得した株式に対して会社側から売渡しを請求できる点に特徴があります。
また、この手続の実務上の重要なポイントとして、以下の点が挙げられます。
- 相続発生から1年以内に請求を行う必要がある(会社法第174条)。
- 相続人は売買価格の決定を裁判所に申し立てることができ、その場合、会社の提示する価格より高い、いわゆる「支配株主価格」で買取らなければならない可能性がある。
さらに実務では、174条の売渡請求が有効に機能するためには、
- 定款に条文が備わっていること
- 譲渡制限株式であること
- 財源規制に抵触しないこと
のほかに、「相続人側の権利保護」とのバランスにも注意が必要です。
相続人は、売渡請求の通知後20日以内であれば、価格決定申立てを行い、裁判所による客観的な株価算定を求めることができるため、会社側の価格提示が低すぎる場合には実質的なチェックが働きます。
また、会社側としては、紛争防止の観点から、
- 適正な第三者算定(株価算定書の取得)
- 相続人への丁寧な説明
- 事業承継計画の中での事前準備
が重要とされます。
即ち、譲渡制限会社の株主が死亡して相続が発生した場合や、その他の一般継承(株主が法人である場合の合併や分割による継承)により、会社にとって好ましくない継承が起こる場合があります。
このような場合、会社が一般承継人に対して売渡し請求を行い、譲渡制限株式を継承する人の同意がなくても株式を取得することができるのです。
相続人に対する相続株式売渡請求(スクイーズアウト)を行うための条件
相続人に対する株式の売渡請求(スクイーズアウト)を行うためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
売渡請求を行う株式が譲渡制限株式であること
譲渡制限株式とは、株式会社が発行する全部又は一部の株式を譲渡により第三者が取得する場合、発行会社の取締役会または株主総会での承認がないと譲渡することができないことを定款に定められている株式のことをいいます。
定款に売渡請求ができる旨を定めていること
売渡請求を行えるようにするためには、相続などにより取得した株式を当該会社に売り渡すことを請求することができる旨の以下の規定を定款に設けておく必要があります。
「当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すことを請求することができる」
このような規定を定款に定めることは、相続が起こった後でもできますが、現在定款に規定が無い場合はあらかじめ規程を設けておいた方がよいでしょう。
相続等があったことを知った日から1年以内に請求権を行使すること
被相続人の死亡から1年を超えた場合は、相続人に対する株式の売渡し請求を行うことはできません。
自己株式の取得が財源規制に違反しないこと
自己株式を取得するための財源は剰余金の分配可能額に制限されるため、債務超過の会社の場合は財源規制を満たしません。
即ち、買い取る資金が十分にない場合は、売渡し請求を行うことができないのです。
例えば、売渡し請求を行った事業年度に欠損が生じた場合には、取締役に補填責任が生じるのです。
そのため、売渡し請求を行った年度に欠損が生じたとしても、次期の決算見込みが財源規制に違反しない可能性があるのならば、次期に相続人等に対する株式の売渡し請求を行うこともできます。但し、③の制限にかからないように注意が必要です。
株主総会の特別決議の承認を得ること
相続人に対する株式の売渡し請求を行うためには、株主総会の特別決議の承認が必要になります。
なお、これらの要件を満たしていないにもかかわらず売渡請求を行うと、手続の無効や紛争化につながるため、特に以下の点が実務上指摘されています。
- 株式が相続人に承継されているかの確認(遺産分割前の共有状態を含む)
- 定款文言が会社法174条の趣旨に沿っているかの確認
- 譲渡制限の範囲(全部か一部か)
- 買取資金の準備状況(分配可能額の計算)
こうした事前チェックは、後の争いを避けるために極めて重要です。
相続人等に対する相続株式売渡請求(スクイーズアウト)の流れ
相続人等に対する相続株式の売渡し請求(スクイーズアウト)を行うには、以下の手順で行っていきます。
相続株式売渡請求の大まかなフローについては、会社法第175条~第177条に具体的な規定があります。これに従い、以下のような流れで手続が進行します。
1【会社法第175条・176条】
株式売渡請求は、株主総会の決議に基づき行われます。相続人はこの決議について議決権を行使できません。なお、相続の発生を知ってから1年経過した場合には、売渡請求権を行使することはできません。
2【会社法第177条】
売渡請求がなされた場合、会社と相続人間で株式の売買価格について協議します。
3【会社法第177条】
相続人は、売渡請求の日から20日以内に裁判所に価格決定の申立てを行うことができます。裁判所が決定した価格で売買が成立します。
4【会社法第177条】
裁判所は、会社の資産状況など一切の事情を考慮して価格を決定します。申し立てが20日以内になされなかった場合、売渡請求は失効します。
株主総会の特別決議
相続人等に対する売渡し請求を行うためにまず行うことは、株主総会の特別決議により売渡請求をする株式の数(種類株式発行会社の場合は株式の種類及び種類ごとの数)と株主の氏名または名称を定める必要があります。
売買価格については、株主総会の特別決議で決議する必要はありません。
売渡請求をする株式の数は、相続人等が保有する株式のすべてである必要はありません。
保有する株式のうちの一部であっても、売渡請求ができることを前提としています。
また、遺産分割が行われる前に相続人等に対する売渡請求を行う場合には、相続される株式は相続人全員の共有状態にあります。
そのため、その場合の株主の氏名または名称は、法定相続人全員を対象にする必要があるのです。
この株主総会の特別決議では、売渡請求の対象となる相続人等の株主は議決権を行使することができません。但し、他に議決権を行使することのできる株主がいない場合は、この限りではありません。
株式の売渡請求は、基本的に支配株主であるオーナー株主以外の株主が亡くなった場合に行われることが多いです。
しかし、売渡請求の対象となる株主が株主総会の特別決議での議決権を行使することができないのは、オーナー株主が亡くなった場合も例外ではありません。
即ち、売渡し請求の対象となる相続人等には議決権がないため、オーナー株主に相続が発生した場合に少数株主のみの決議によって売渡し請求を決定することができるのです。
そのため、オーナー株主の相続人等が、会社から排除されることや持株比率が減少することにより支配権を失う可能性があります。
このように、相続を契機に会社の乗っ取りのリスクも考えられるため、売渡請求の制度の導入にあたっては注意が必要です。
オーナー株主が亡くなった場合に支配権が移動することを予め防ぐには、オーナー株主が有する株式以外の株式を相続人に対する売渡請求の議案の議決権制限株式としておくことが考えられます。
また、法人を設立してオーナー株主の有する株式をその法人に持たせることにより、支配権の移動を防ぐことができます。
相続株式売渡請求(スクイーズアウト)の通知
株主総会の特別決議を行ったら、決議に基づき、売渡し請求に係る株式の数(種類株式発行会社の場合は株式の種類及び種類ごとの数)を明示して、売渡請求の対象とした株主へ請求(通知)を行います。
売渡請求の通知は、書面で請求することを特に法律で求められているわけではありませんが、後々のことを考えると書面での請求の方がよいでしょう。
会社法上では、この通知に売買価格を明示することは必ずしも求められていません。
しかし、会社側が一定の評価をして、売買価格を提示することが通常です。
この売渡請求の通知により、会社と相続人等との間で株式の売買契約が当然に成立することになります。
そのため、通知を受けた相続人等は、株式の売り渡しを拒むことはできないのです。
また、売渡請求は会社法上でいつでも撤回できるとされていて、その撤回事由は特に制限されていません。
売渡請求は、会社法では相続その他の一般承継があったことを知った日から1年以内に行わなければならないとされています。
相続その他の一般承継があったことを知った日とは、相続の場合は被相続人の死亡の事実を知った日となり、特定の相続人が株式を取得したことを知った日や遺産分割が確定した日ではありません。
また、遺産分割協議が終わっているかわからない場合には、相続される株式は法定相続人全員の共有状態にあるものとして、相続人全員に対して相続した株式の全部を明示して売渡請求を行うとよいでしょう。
売渡請求の事後に遺産分割協議が成立すると、相続割合が変動するなどの問題も生じる可能性がありますので注意が必要です。
相続株式売買価格の協議・決定
売渡請求の通知が行われた場合に、一般的には会社と相続人等の当事者間で株式の売買価格を協議をして決定することになります。
この協議で株式の売買価格が問題なく決定できればよいのですが、協議が整わないケースもあります。
相続株式売買価格の決定を裁判所に申立することができる
このように協議が整わない場合は、会社または相続人等は、裁判所に対し売買価格決定の申立てをすることができるのです。
但し、この申立ては、売渡請求があった日から20日以内行われなければなりません。
売渡請求があった日から20日以内に当事者間の協議も整わず、売買価格決定の申立てもなされなかった場合には、売渡請求の効力は失われるのです。
そのため、協議が整わないような場合には、なるべく早めに裁判所への売買価格決定の申立てを検討する必要があります。
また、会社法では売買価格決定の申立てを行う前提条件に事前の協議は含まれていないため、協議を行わずに裁判所に対して申立てを行うこともできるのです。
売買価格決定の申立てを行う場合、会社または相続人等は主張する売買価格が適正であることを疎明する一定の資料を準備しておく必要があります。
特に会社側から申立てを行う場合は、売買価格が適正であることを疎明することがとても大切になります。
相続株式売買価格裁判における株式売買価格
申立てを受けた裁判所は、鑑定人による適正な価格の意見を聞くとともに、会社の資産状態その他一切の事情を考慮することにより売買価格を判断します。
会社側はこの一切の事情を裁判所に考慮してもらうために、株式を買い取る必要性などの事情を十分に説明する必要があるのです。
会社法では売渡請求により株式を取得する場合、株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされています。
即ち、会社法では債権者への支払いを確保できるだけの財産を残すことにより、初めて株主へ利益を配分することができるとしているのです。
そのため、分配可能額とは、この債権者への支払いを確保できるだけの財産の額と考えられます。
売渡請求により株式を取得するためには、買取資金についても十分に考えておく必要があるのです。
価格決定申立てにおいて裁判所が考慮する「一切の事情」には、
- 会社の資産・負債
- 事業価値
- 類似会社比準方式やDCF方式等の一般的な株価算定方法
- 会社と相続人の交渉経緯
などが含まれ、単純な純資産価値だけで決まるものではありません。したがって、会社側としては、客観的な株価算定資料の取得と、買取りの合理性の説明資料の準備が極めて重要となります。
まとめ
このように、会社は株主が亡くなった時にその相続人に株式を保有させたくない場合には、相続人等に対する売渡請求を行うことがとても有効な手段になります。
そのため、相続による株式の移動を防ぎたい会社は、よく検討をして相続人等に対する売渡請求を行えるように準備をしておくとよいでしょう。
相続に伴う株式承継は、中小企業の事業承継において大きな影響を及ぼす場面です。株式の分散、相続人の意向の不一致、経営参加能力の問題などにより、会社経営が不安定化する例も少なくありません。
こうしたリスクを未然に防ぐためには、
- 事前の定款整備
- 譲渡制限株式の適切な設定
- 事業承継計画の策定
- 必要に応じた専門家(弁護士・税理士等)への相談
が重要です。相続発生後に慌てるのではなく、事前に制度を理解し、会社の状況に応じた準備を進めておくことで、円滑な事業承継と会社の安定した経営が可能になります。