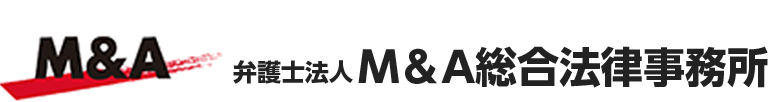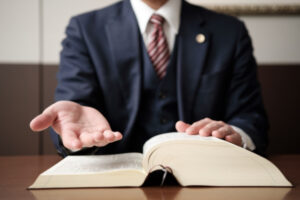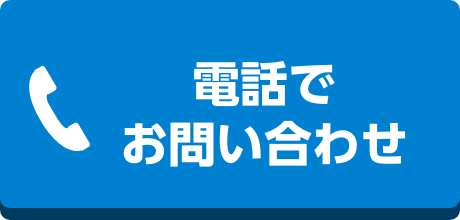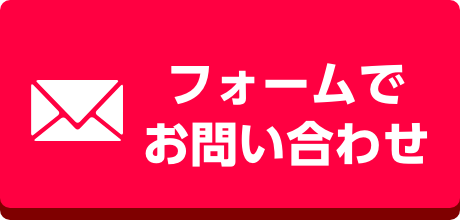相続人に対する株式売渡請求権(スクイーズアウト)の内容とメリット・デメリット!
お困りではありませんか?

この記事では、そんな株式等売渡請求(スクイーズアウト)のうち相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)の制度について、その内容と、メリット・デメリットや手続きの内容などの情報についてM&A弁護士が徹底解説していきます。
相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)
相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)とは
相続人に対する株式等売渡請求は、会社法第174条から第177条に規定される制度であり、会社が相続人からの個別の承諾なく金銭を対価として円滑に株式を取得することを目的として制定された制度です。
会社法第174条第1項では「株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。」と規定しており、この制度の基本的な枠組みを定めています。
この制度により、各相続人に売渡請求を行えば、半ば強制的に後継者に株式を集中させることが可能であるため、円滑に事業承継を実施するために株式等売渡請求(スクイーズアウト)は欠かせない手続きといえます。
相続により株式が分散した場合、従来は各相続人との個別交渉により株式を買い取る必要がありましたが、相続人の数が多い場合や相続人との関係が良好でない場合には、株式の集約が困難となる問題がありました。平成26年の会社法改正により導入されたこの制度により、このような問題に対する法的な解決手段が提供されることとなりました。
相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)の条件
相続人に対し株式等売渡請求を行う場合、以下のような条件をクリアする必要があります。
時期的要件
会社法第175条第1項により、相続の事実を知ってから1年以内に株式等売渡請求(スクイーズアウト)を行使する必要があります。同条項では「株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りでない。」と規定しており、この期間は除斥期間であり、延長することはできません。会社が相続の事実を知った時点が起算点となるため、相続開始時期と異なる場合があることに注意が必要です。
財務的要件
会社法第461条第1項の分配可能額の範囲内で株式買取を実行する必要があります。分配可能額は、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計となります。分配可能額が不足する場合には、株式等売渡請求を行うことができません。これは自己株式の取得が分配可能額の範囲内で行われなければならないという会社法の原則に基づくものです。
株式の性質に関する要件
会社法第174条第1項により、株式等売渡請求(スクイーズアウト)の対象は譲渡制限株式に限定されています。同条項では「当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)」と明記されており、譲渡制限が付随していない場合は、請求を行うことは不可能です。譲渡制限株式とは、会社法第107条第1項に規定される株式であり、株式会社が発行する全部又は一部の株式を譲渡により第三者が取得する場合、発行会社の取締役会または株主総会での承認がないと譲渡することができないことを定款に定められている株式のことをいいます。
相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)の手続き
相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)には、以下のような必要な手続きがあります。
定款の定めの整備
会社法第174条第1項に基づき、定款に相続人への売渡請求(スクイーズアウト)を実行できる旨を定める必要があります。売渡請求を行えるようにするためには、相続などにより取得した株式を当該会社に売り渡すことを請求することができる旨の規定を定款に設けておく必要があります。具体的には「当社は、相続その他の一般承継により当社の株式を取得した者に対し、当該株式を当社に売り渡すことを請求することができる」との規定を定款に定めます。
株主総会特別決議
会社法第175条第2項及び第176条に基づき、株式等売渡請求を行う株式数と対象者の氏名について、特別決議を実施します。会社法第175条第2項では「株式売渡請求は、株主総会の決議によって、売渡請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)及び株主の氏名又は名称を定めて行わなければならない。」と規定されています。売買価格については、株主総会の特別決議で決議する必要はありません。
売渡請求の通知
特別決議で可決された場合、対象者に売渡請求の通知を行い、対象者と会社側で売買価格を決定します。
売買価格の決定
会社法第177条第1項により、売買価格はまず相続人との協議によって定めます。同条項では「売買価格は、株式会社と当該株主との協議によって定める。」と規定されています。
協議が整わない場合は、会社法第177条第2項に基づき、裁判所に売買価格を決定してもらうことが可能です。同条項では「会社又は当該株主は、売渡請求があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。」と規定されており、株式等売渡請求(スクイーズアウト)から20日以内に申し立てを行う必要があります。売買価格が決定すれば、株式の売渡を実行することが可能となります。
株主総会の特別決議が必要
会社法第309条第2項第11号により、定款の変更には株主総会の特別決議が必要です。定款の変更については、予めしておくこともできますし、相続人に対する株式等売渡請求権(スクイーズアウト)を行使するときに行うこともできますが、いずれの場合も特別決議が必要となります。また、会社法第175条第2項により、株式等売渡請求(スクイーズアウト)を発動するためにも株主総会の特別決議が必要ですので、相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)を行うためには、株主総会の特別決議が必要です。
株主総会の特別決議とは、会社法第309条第2項により、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければなりません。したがって、株主の3分の2以上が賛成しないと、相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)を発動することができません。
なお、会社法第175条第3項により、当該相続人は、この株主総会において議決権を行使することができません。ただし、会社法第175条第1項ただし書により、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から1年を経過したときは、この限りではありません。
株式等売渡請求(スクイーズアウト)のメリット
株式等売渡請求(スクイーズアウト)は、非常にメリットの多い権利です。
経営権を集中させることができる
会社の歴史が長くなってくると、親族間などで株式が分散してしまっていることがあります。事業を承継する場合、後継者に経営権を集中させるために、できるだけ分散している株式を集約しておきたいと考えるのが通常です。株式等売渡請求(スクイーズアウト)を行使すれば、半ば強制的に経営権を集中させることが可能となっています。
節税効果に期待できる
株式等売渡請求(スクイーズアウト)による自社株の買収は、節税効果にも期待できます。
通常、非上場企業が自社株を取得する際には、「みなし配当課税」が生じてくるのが一般的です。みなし配当課税は、配当所得は他の所得と総合して課税され、最高で「50%(所得税率45%・住民税率5%)」もの税金が課せられてしまいます。
しかし、株式等売渡請求(スクイーズアウト)により相続人から株式を取得した場合、それは「譲渡所得」とみなされるため、課税額も一律で「20.315%」で済ませることができます。
事業承継時において、いかに節税するかは悩みの種でしょう。よって、軽い税負担で自社株を取得できるというのは、非上場企業の事業承継において大変魅力的なメリットとなっているのです。
法的な強制力
相続人の個別の承諾を得ることなく株式を取得できるため、相続人との関係が良好でない場合や、相続人が多数存在する場合であっても、確実に株式を集約することができます。
株式等売渡請求(スクイーズアウト)のデメリット
しかし、その反面少なからずデメリットも存在するため、ここでは株式売渡請求権(スクイーズアウト)のデメリットを解説していきます。
株式売買価格が交渉により決着しない場合、裁判になる可能性がある
会社法第177条第1項により、売買価格は、まずは、相続人との協議によって定めますが、協議が整わないときには、会社法第177条第2項に基づき、会社または相続人は、売渡請求があった日から20日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができます。
この場合、会社法第177条第4項により、裁判所は「売買価格の決定をするときは、売渡請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。」とされており、最終的には、裁判所が、公正な価格を決定いたしますので、会社としては、相続人から、安く株式を買い取ってしまうということはできません。
相続人に対する株式等売渡請求(スクイーズアウト)の場合は、会社都合による株式の買取ですので、相続人から少数株主であることを前提としたディスカウントされた株価(配当還元法など)に基づく株式売買価格の決定が行われるのではなく、組織再編に伴う株式買取請求権(スクイーズアウト)のようにディスカウントの無い株価(時価純資産法や収益還元法)に基づく株式売買価格の決定が行われるものと思われ、会社としては、株式売買価格が想定外に高騰する可能性もあります。
手続きの複雑性
株主総会の特別決議が必要であり、かつ厳格な手続要件が定められているため、手続きの実施に相当の時間と労力を要することとなります。また、手続きに瑕疵がある場合には、株式等売渡請求の効力が否定される可能性もあります。
分配可能額による制約
株式の買取価格の支払いは分配可能額の範囲内で行う必要があるため、会社の財務状況によっては制度を利用できない場合があります。分配可能額が不足する場合には、増資等により分配可能額を増加させる必要があり、追加的なコストが発生します。
実務上の留意点
定款の定めの時期
相続人に対する株式等売渡請求に関する定款の定めは、相続開始前に整備しておくことが望ましいといえます。相続開始後に定款変更を行う場合、相続人が株主となっているため、特別決議の可決に相続人の協力が必要となる場合があります。
株式価格の事前検討
裁判所による価格決定手続きに移行した場合の株式価格を事前に検討し、買取資金の調達可能性を確認しておくことが重要です。特に、企業価値の高い会社の場合には、想定以上の買取資金が必要となる可能性があります。
相続人との事前協議
法的には相続人の承諾を得る必要はありませんが、可能であれば事前に相続人と協議を行い、制度の内容や株式価格について説明しておくことが望ましいといえます。これにより、手続きの円滑な進行と紛争の回避を図ることができます。
まとめ
『株式等売渡請求(スクイーズアウト)』を活用することにより、以前よりも容易に100%子会社化などが実施できるようになったのは間違いありません。
ただし、株式等売渡請求(スクイーズアウト)を用いることができる場面や条件は限定されており、複雑なプロセスも存在していることから、成功させるためにはどうしても専門的な知識が必要となります。
相続人に対する株式等売渡請求制度は、事業承継において株式の集約を図るための有効な手段として位置付けることができます。相続人の個別の承諾を得ることなく株式を取得できる点で、従来の制度と比較して利便性が向上しています。
一方で、厳格な要件と手続きが定められており、また株式価格の不確実性等のリスクも存在することから、制度の利用に当たっては慎重な検討が必要です。特に、裁判所による価格決定手続きに移行した場合の株式価格については、事前に専門家による評価を受けておくことが望ましいといえます。
よって、株式等売渡請求(スクイーズアウト)を行使する場合は、株式等売渡請求(スクイーズアウト)はもとより、M&Aや事業承継に特化した弁護士のアドバイスを受けることをご検討ください。
お困りではありませんか?