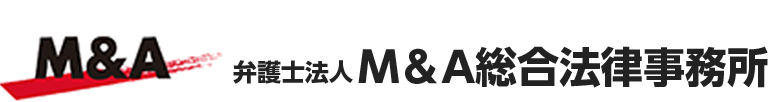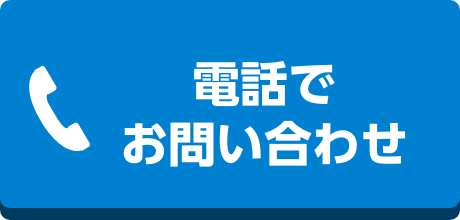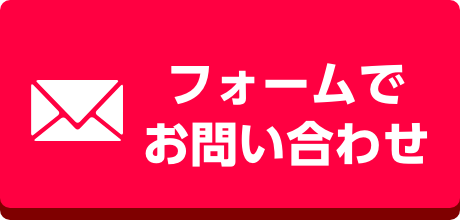非上場会社における株式譲渡制限制度の実務的解説
お困りではありませんか?

はじめに
非公開会社(譲渡制限会社)では、すべての株式に譲渡制限が付され、株式の譲渡には会社の承認が必要です。
この株式譲渡制限制度は、望ましくない第三者が株主となることを防止し、会社の安定的な支配権維持に重要な役割を果たしています。
本稿では、株式譲渡制限制度の趣旨・法的根拠と基本構造、戦後における立法の変遷、譲渡承認拒否時の会社または指定買取人による株式買取義務の要件と限界、株式買取価格評価方法の差異によるリスク、制度を悪用する株式買取業者への対応策、さらに実務上発生したトラブル事例(みなし承認や承認機関を株主総会とした場合の問題点)について、経営者向けに専門的かつ平易に解説し、各トピックについて、会社法の規定や判例・実務の知見を踏まえ、必要に応じて出典や根拠を明示しながら論じます。
1. 株式譲渡制限制度の趣旨・法的根拠と基本構造
制度趣旨
株式の譲渡制限制度は「会社にとって好ましくない者が株主となることを防止する」ために設けられたものです。
株式は本来自由に譲渡できることが原則ですが(会社法第127条)、非公開会社では株主を信頼関係のある者に限定し、経営支配の安定を図る必要が高いため、会社法は定款で譲渡制限を定めることを認めているのです。
具体的には、会社法第107条第1項第1号・第108条第1項第4号により、「株式会社が発行する株式の譲渡による取得について当該会社の承認を要する」という内容を定款に定めることで、その株式を譲渡制限株式とすることができます。
この定款の定めによって譲渡制限が付された株式を発行している会社を譲渡制限会社(非公開会社)といい、発行株式の一部でも譲渡制限のない株式が含まれる会社は公開会社と定義されています(会社法第2条第5号)。
なお、「公開会社」は必ずしも上場会社を意味せず、実際に株式市場で流通していない非上場会社であっても定款で譲渡制限を付していなければ会社法上は公開会社となる点に留意しましょう。
法的根拠と基本構造
上述のように、株式譲渡制限制度の直接の根拠規定は会社法第107条第1項第1号等であり、定款により株式の内容として譲渡に会社の承認を要する旨を定めることが可能です。
この制度の下では、株式譲渡の際に会社の承認を要するという仕組みが基本構造となります。承認機関は原則として取締役会設置会社では取締役会、取締役会を置かない会社では株主総会ですが(会社法第139条第1項)、定款により承認機関を柔軟に変更することもできます。
例えば、「代表取締役を承認機関とする」「特定の役職者(執行役等)を承認機関とする」ことも許容されており、迅速な意思決定のために承認権限を少人数に委ねる設計も実務上行われています。
また、定款で別段の定めをすれば、「特定の場合には承認不要」(例:既存株主間の譲渡や特定範囲内の譲渡は自由とする)といった承認不要となる譲渡の範囲を定めることも可能です(会社法第107条第2項、第139条但書)。
このように会社法は譲渡制限を株式の一内容として位置付けており、会社ごとの実情に応じて柔軟な制度運用ができるのです。
2. 戦後の立法経緯による制度変遷(昭和23年商法改正~平成17年会社法制定)
戦後すぐの商法改正(昭和23年~昭和25年)
戦前の商法では、定款自治の範囲で株式譲渡を制限・禁止することも広く認められていましたが、日本経済の民主化と活性化を図る戦後改革の中で、株式譲渡自由の原則が重視されるようになります。
昭和23年の商法改正および続く昭和25年(1950年)の商法改正では、株式譲渡の自由が絶対的に保障される立場が採られ、定款による過度な譲渡制限は認められなくなりました。要するに、戦後間もない時期には「株式は自由に譲渡できるべきもの」との理念が強調され、閉鎖的な株主構成を維持することよりも株式流通の円滑化が優先されたのです。
譲渡制限制度の復活(昭和41年商法改正)
しかし、中小企業や同族会社などでは株主構成の安定が重要であるため、全ての会社に株式譲渡の絶対的自由を貫徹することには問題がありました。
このため、昭和41年(1966年)の商法改正において、現在に近い形態の定款による株式譲渡制限制度が導入されます。
この改正により、非上場企業等では定款で株式譲渡制限を付すことが再び可能となり、会社の承認なくして譲渡された場合の取扱いや、承認拒否時の会社側の対応についての規定(現在の会社法第204条の前身にあたる規定など)が整備されました。
つまり、1960年代後半以降、閉鎖会社的な株主構成を維持する制度的枠組みが復活・定着したのです。
以後、この譲渡制限制度の下で「会社の承認なき譲渡の効力」について学説上は絶対無効説と相対的無効(対抗不能)説が対立し、判例上は後述のように相対的無効の立場(会社に対して効力を生じないが当事者間では有効)が採られていきました。
会社法制定(平成17年)による制度拡充:平成17年制定・平成18年施行の会社法(現行法)は、商法等の改正を包括的に行い、株式譲渡制限制度についてもさらなる拡充・柔軟化を図りました。
まず、株式会社の類型として「非公開会社」「公開会社」の区別が明文化され(会社法2条5号、非公開会社は発行株式全部に譲渡制限あり)、譲渡制限は株式の種類内容として位置付けられました(会社法107条・108条)。
これにより、一部の株式だけ譲渡制限を付す種類株式を発行することも可能となり、例えば上場会社であっても特定の種類株式(いわゆる黄金株など)にのみ譲渡制限を付けることができるのです。
逆に非公開会社であっても、新株発行による資金調達時に投資ファンド向けの株式だけ譲渡制限を付さない(譲渡の自由な優先株式を発行する)ことも可能になりました。
これらにより、事業承継やベンチャーファイナンスの場面で柔軟な株式設計ができるようになりました。
また、会社法では譲渡承認機関の変更(取締役会以外への委任)を明文で認め、相続等による包括承継の場合に会社が相続人に対して株式の売渡請求をできる制度(会社法第174条~第177条)も導入されました。
このように平成17年会社法は、閉鎖性の担保と機動的な企業活動(資本政策)の両立を図るべく制度を現代化したと評価できます。
3. 譲渡承認拒否と会社(または指定買取人)による株式買取義務の要件・限界
承認拒否と買取請求権の発動
譲渡制限株式について株主または譲受人から譲渡承認請求があった場合、会社は定款で別段の定めがない限り所定の機関(取締役会または株主総会)で承認するか否かを決定します(会社法第139条第1項)。
会社が承認しない決定をする(=譲渡を拒否する)ことももちろん可能ですが、そのままでは株主が株式を現金化できず不都合が大きいため、会社法は救済措置として株主による買取請求権を定めています。
すなわち、譲渡承認を求める請求(会社法第136~137条)をする際に、請求者(譲渡人または譲受人)は会社が承認しない場合には会社又は会社指定の第三者に株式を買い取らせるよう求めることが可能です(会社法第138条第1項但書・同第1号ハ、同第2号ハ)。
実務上は承認請求書に「不承認の場合は買取請求する」旨を明記して請求することになります。
この買取請求がなされた場合、会社が譲渡を承認しなかったときは、会社自身が買い取るか、第三者(指定買取人)に買い取らせるかを決定する義務が会社に生じます(会社法第140条)。
これは、譲渡を拒否する以上は株主の退出手段を用意すべきという制度趣旨に基づくものなのです。
手続の要件と流れ
承認拒否→買取の一連の手続は、会社法136条以下に詳細に規定されています。
概要を時系列で整理すると、まず譲渡承認請求の受領を起点に、会社は2週間以内に承認可否を決定し通知しなければなりません(会社法139条2項、145条1号)。
この2週間の期限内に会社が何ら通知しなかった場合、会社が承認したものとみなされます(みなし承認)。
したがって非公開会社では、請求から2週間という短期間で株主総会開催や取締役会決議を経て通知する迅速な対応が求められ、経営者がこのタイムリミットを失念すると、意図せぬ株主異動(みなし承認)を招くことになります。
会社が譲渡を承認しないと通知した場合、同時に買取請求への対応を取らなければなりません。
すなわち、不承認の通知において「承認しない」旨だけでなく(請求があった場合には)「会社が買い取るか指定買取人を指名する」旨も通知する必要があるのです。
もし請求者が買取請求をしていなかった場合は単に譲渡不承認となり取引自体が無効に帰しますが、実務上は株主が出口確保のため必ず買取請求を付すのが通例です。
譲渡承認請求・買取請求があった場合の手続き概略(不承認時)
会社が譲渡承認請求に対して承認しない旨を決定した場合で、請求者が不承認時の株式買取を求めているときは、その後の手続は二つの経路に分かれます。
すなわち、会社自らが当該株式を買い取る経路と、会社が指定する第三者(指定買取人)が買い取る経路です(会社法第140条)。
まず、会社自らが買い取る経路を選択する場合には、自己株式の取得に該当するため、会社は株主総会の特別決議により、会社が買い取る旨および買い取る株式数を決定する必要があります(会社法第140条第2項、同第309条第2項第1号)。
この決議を経たうえで、会社は不承認の通知の日から四十日以内に、会社が買い取る旨を請求者に通知しなければなりません(会社法第145条第2号)。
この期限までに買い取りの通知をしないときは、会社が譲渡を承認したものとみなされます。
なお、会社が自己株式を取得する場合は、分配可能額などの財源規制の適用を受けます(会社法第461条、同第465条)。
他方、指定買取人が買い取る経路を選択する場合には、会社は取締役会決議等により第三者を指定し(会社法第140条第4項・第5項)、その指定を受けた第三者は、不承認の通知の日から十日以内に、指定を受けた第三者が買い取る旨および買い取る株式数を請求者に通知します(会社法第142条第1項)。
この通知がなされると、請求者と指定買取人との間で売買契約が成立することになります。
指定買取人は、通知に続いて遅滞なく売買代金を供託することが予定されており(会社法第141条第3項、同第142条第1項)、供託が適切に行われない場合には、会社または指定買取人による契約解除が認められるようになります(会社法第141条第4項、同第142条第4項)。
いずれの経路においても、売買価格は当事者間の協議によって定めるのが原則であり(会社法第144条第1項)、協議が整わない場合には、買い取りの通知があった日から二十日以内に、当事者のいずれからでも裁判所に対して売買価格の決定を申し立てることができます(会社法第144条第2項)。
裁判所は、譲渡承認請求時点における会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格を定めます。
申立てが行われず、かつ協議も整わない場合には、供託された金額が売買価格として確定します(会社法第144条第5項・第7項)。
これらの手続には厳格な期限が設けられており、会社は、①譲渡承認請求の受領後二週間以内に承認可否を決定して通知する義務(会社法第139条第2項)、②不承認とした後四十日以内の会社買い取り通知の義務(会社法第145条第2号)、③指定買取人を選択した場合の十日以内の買い取り通知義務(会社法第142条第1項)を順守しなければなりません。
これらの期限を徒過した場合には、譲渡承認がみなされるなど、会社側に不利益な効果が生じます(会社法第145条)。
買取価格の決定方法と限界
承認拒否に伴う株式買取において核心となるのが、売買価格の決定です。
会社法第144条に詳細な規定がありますが、基本は当事者(会社・指定買取人と株主)間の協議で価格を決めます(会社法144条1項)。
現実には、会社側(買い手側)と売主株主側との間で株価の認識に大きな開きがあることもしばしばで、協議が整わないことも多いでしょう。
その場合、買取通知があった日から20日以内であれば、双方当事者は裁判所に売買価格の決定を申立てることができます(会社法144条2項)。
裁判所は「譲渡承認請求時における会社の資産状態その他一切の事情」を考慮して価格を決定することとされ(144条2項本文)、公正な価格算定が図られます。
もし20日以内に申立てがなく協議も整わない場合、供託された金額がそのまま売買価格となります(144条5項、7項)。
なお、会社自身が買い取る場合には、その取得は自己株式取得に当たるため、分配可能額を財源とする必要があるなどの財源規制が適用されます(会社法461条・465条)。
十分な剰余金がない会社が高額な少数株を買い取ることは法的にも困難であり、資金面で制約がある点も会社側の限界です。
以上のように、承認拒否から株式買取に至る一連のプロセスは法定の厳格な期限と手続きを伴い、対応を誤ると期限経過によるみなし承認や手続無効といったリスクが常につきまとうのです。
特に非公開会社の経営者は、「2週間以内の承認可否決定」「不承認なら40日以内の買取実行」等のスケジュールを正確に把握し、社内で迅速な意思決定ができる体制を整えておく必要があります。これらの手続は期限を徒過すると重大な不利益を招くおそれがあるため、必要に応じて専門家の助言を仰ぎましょう。
4. 株式買取価格の評価方法(国税庁方式 vs 経済学的手法)と評価額の差によるリスク
譲渡制限株式の売買価格を算定するにあたっては、大きく分けて「国税庁方式」と呼ばれる財産評価基準に基づく手法と、「経済学的手法」(企業価値評価手法)という2つのアプローチがあります。
前者は主に相続税評価など税務上の評価に用いられる方式で、具体的には国税庁の定める『非上場株式の評価方式』に従い類似業種比準価額法や純資産価額法等で評価額を算出するものです。
これは会社の純資産額や類似業種上場会社の株価指標に基づき画一的に評価する手法で、企業の内在的な将来価値やシナジー等は織り込まれない傾向といえます。
一方、後者の経済学的手法とは、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)や市場株価倍率法(類似企業のPERやEBITDA倍率を基にする方法)など、企業の収益力や将来性を考慮した評価で、より実態に即した投資価値・経済価値を反映する株価を算定します。
実務上問題となるのは、これら二つの評価額に大きな乖離が生じる場合のリスクがあります。
典型的なのは、国税庁方式では低く評価される一方で、経済学的手法では高い評価額が出るケースです。
たとえば中小の同族会社で純資産はそれほど大きくなくとも収益力が高い企業では、税務上は純資産基準で低い株価が算定されがちですが、DCFなどで評価すると将来キャッシュフローに基づき相当に高い株価が算定されることがあります。
逆に、純資産が厚く蓄積されている優良企業では純資産基準の評価額自体が高額となり、これが買取価格算定の基準とされると会社や買手にとって大きな負担となるのです。
特に業績好調で内部留保が厚い企業ほど純資産価額基準の株価が高騰するため、そのような企業が株式買取業者の標的になりやすいとの指摘もされています。
実際、近時話題となっている株式買取業者(後述)の手口では、相続税評価額等の低い価格で株式を買い取っておき、会社に対しては収益力に見合う高い価格で買い取らせて差益を得るというケースが見られます。
これは、まさに評価方法の差異を突いた利益追求であり、非公開会社の経営者にとって看過できないリスクといえるでしょう。
法的手続き面では、先に述べた売買価格決定の申立て(会社法144条)において裁判所が会社の資産状態その他一切の事情を考慮して価格を決定する以上、純資産額や収益力、さらには同業他社の状況や株式市場の動向など様々なファクターが考慮されることになります。
したがって、裁判所の判断する「公正な価格」は、国税庁方式とも単純なDCF評価とも異なる総合的な評価額となる傾向があります。
しかし、それでも事案によりどの評価手法に重きを置くかで数倍の開きが生じる可能性があり、当事者の主張次第では評価額の攻防が熾烈になるでしょう。
経営者としては、自社株の評価額がどの程度になるのか(税務評価額と潜在的経済価値の差はどのくらいあるか)を平時から把握しておき、万一の買取請求に備えて適切な価格での買収原資を準備しておかなければなりません。
例えば、「自社の税務上の評価額は1株○円だが、事業計画を反映したDCF評価では○円となる」といった情報を押さえておけば、いざという時の価格交渉や裁判所での主張立証にも備えができます。
逆にそうした準備なく買取請求に直面すると、過大な支出を強いられキャッシュフローが逼迫したり、価格交渉が決裂して余計な訴訟に発展するリスクが高まります。
評価方法の違いによるギャップは経営上のリスクであると認識し、株主構成の変動に備えるべきでしょう。
5. 株式譲渡制限制度を悪用する株式買取業者の動向と企業側の予防・対応策
近年、未上場会社の少数株主に対し接近して株式を買い取り、会社に買い取らせることで利ざやを稼ぐ「株式買取業者」と呼ばれるビジネスモデルが注目されています。
典型的な手口は次のようなものです。
まず業者は非公開会社の少数株主(しばしば創業者一族から離れた親族や元従業員、相続で株式を取得した者など、会社と利害関係の薄い株主)に接触し、その株式を相続税評価額など比較的低い価格で買い取ります。
本来、譲渡制限株式の譲渡には会社の承認が必要ですが、業者側は当然会社が承認しないだろうことを織り込み済みです。
そこで最初から会社に対し譲渡承認請求と「不承認の場合の買取人指定請求」を行い、会社が承認しなければ買取手続に移行させます。
会社としては、見ず知らずの業者を新株主として受け入れるわけにはいかない(まさに「好ましくない者が株主となることを防止」するため譲渡制限を設定している)ので、承認せずに会社または指定買取人が株式を買い取らざるを得ない状況に追い込まれます。
そこで業者の狙い通り、裁判所の売買価格決定手続き等を通じて会社側に高値で買い取らせ、最初に安値で買った価格との差額分を利益として得るという仕組みです。
特に業績好調な企業では前述のとおり、純資産基準等で株価が高く算定される傾向があるため、そのような会社ほど標的になりやすいのが実情です。
実際、「親族株主が相続税負担に苦しんでいるところに業者が現れ、『譲渡制限株式だが当社で買い取ります』と勧誘して株式を取得→会社に対し高額での買い取りを請求」という事例報告が各所で聞かれるようになっています。
このような譲渡制限制度の盲点を突いた株式買取業者への対策として、企業側は事前・事後で以下のような対応策を講じることが望ましいでしょう。
事前の予防策
まず基本として、自社の株主が第三者に株式を売却する動きを察知したら早期に対話し、会社または信頼できる関係者が先買権を行使するなどして、業者に株式が渡らないようにすることです。
特に相続が発生した場合、会社は会社法第174条に基づき相続人に対して1年以内であれば、株式の売渡請求(強制買取)を行うことが可能ですので、この権利行使も検討します。
相続人が会社と疎遠な場合でも、放置すれば業者に接触される可能性があります。
したがって、相続発生の情報を把握したら迅速に適正価格での自社株買い取りオファーを提示し、相続人に現金を渡してでも株式を会社側に留め置くことが重要です。
加えて、平時から定款の譲渡制限規定を再点検し、抜け穴がないか確認します。
例えば譲渡承認機関や手続きが不明確だと、業者に付け入る隙を与える可能性があります。また可能であれば主要株主間で株主間契約を締結し、第三者への譲渡時には会社や他の株主に買取の優先交渉権を与える等の取り決めをしておくことも有効です。
これにより内部の株式が外部に流出しにくくなります。
事後の対応策
それでも業者による承認請求が起こってしまった場合、拙速に譲渡を承認しないことが肝要です。
一見、承認して業者を株主にしてしまえば会社として買取資金を払わずに済みますが、「好ましくない株主」を内部に入れるデメリットは計り知れません。
業者は純投資家ではなく短期利益を目的としているため、株主権を乱用して経営を妨害したり、最終的には高値で買い取らせるよう仕向けてくる可能性が高いです。
従って安易な譲渡承認は避け、かならず専門の弁護士に相談の上で最善策を検討すべきです。
場合によっては、承認を拒否して買取手続に入った後、買い取り価格の交渉において専門家の鑑定意見を活用したり、必要なら裁判所で適正価格を争うことも視野に入ります。
近時の大阪高裁令和6年7月12日判決では、ある株式買取業者と少数株主との間の売買契約について、弁護士法第73条(非弁行為の禁止)違反で無効と判断した事例も出ています。
このケースでは業者の行為態様に特殊事情があったとはいえ、会社が毅然と法的反撃を行った一例です。
自社が業者による株式買取ビジネスの標的とされてしまった場合、諦めずに法的方策を検討する価値はあります。具体的には、業者の行為が非弁提携や信義則違反に該当しないか主張するとともに、時間稼ぎ策として他のホワイトナイトとなる買い手を用意し交渉を引き延ばす、といった実務策も考えられます(ただし前述の法定期限に制約されます)。
いずれにせよ、こうした複雑な対応には高度な法的知識を要するため、株式譲渡承認請求や売買価格決定の申立てに直面したら直ちに専門家と連携することが肝心です。
以上のように、株式買取業者への対応は事前予防と事後の迅速・的確な対処の両輪が重要といえるでしょう。
幸いにも会社法の規定は会社側に短いながら時間的猶予と選択肢を与えてくれているので、経営者は平時から体制を整え「いざという時には専門家とともに迅速に動く」準備をしてください。
そうすれば、たとえ少数株主絡みのトラブルが発生しても、望ましくない株主の会社支配への侵入や、経済的に不合理な高値買い取りを可能な限り回避し、会社の経営権・支配権を守ることができるでしょう。
6. 実務上のトラブル事例と留意点(みなし承認例、承認機関を株主総会とする場合の問題点)
非公開会社の株式譲渡制限制度下では、実務上いくつか典型的なトラブルが報告されています。
ここでは特に「(1)「みなし承認」による想定外の株主異動」と、「(2)承認機関を株主総会と定めた場合の問題点」の二点について取り上げます。
みなし承認となった事例
前述のとおり会社法第145条は、会社が一定期間内に譲渡承認可否の通知や買取通知を行わなかった場合に承認したものとみなす規定を置いています。
この「みなし承認」制度は、請求者保護と迅速な法的安定のため設けられたものですが、一方で会社側の対応遅れによる不本意な株主異動という事態を招きかねません。
実務でも、例えば経営者が請求に気付かず対応が遅れた結果、2週間を過ぎてしまい第三者への譲渡が自動承認されてしまったケースがあります。
ある中小企業では、代表者宛に送付された株式譲渡承認請求書が事務ミスで放置され、2週間後に全く意図しない人物が株主名簿上株主となっていたという事例が報告されています。
その株主は競合関係者であったため、会社は慌てて当該株主との交渉による自己株買い(もしくは株式併合による排除など)を検討せざるを得なくなりました。
みなし承認となった株式譲渡は有効に成立してしまうため(会社は拒否権を喪失する)、後から覆す法的手段は基本的に存在しません。
このような事態を避けるには、まず譲渡承認請求の通知先を適切に管理すること(本店住所宛の内容証明などは見逃さない体制)、社内で請求を受けた場合の迅速な稟議ルートを構築しておくことが必要です。
また、代表者不在時でも期限管理ができるよう複数担当者でフォローする体制も望ましいでしょう。
みなし承認が起きてしまうと打つ手は限られます。
新株主との任意交渉で株式を買い戻す、あるいは会社法上の株式併合・全部取得条項付種類株式などの少数株主排除スキームを用いる、といった手段も検討されますが、いずれも時間・コストがかかる上に新株主の協力が得られなければ実現困難です。
結局のところ、みなし承認を起こさないのが最善策であり、そのためには社内の法務管理体制の整備こそ最大の予防策となります。
承認機関を株主総会とする場合の問題点
会社法第139条ただし書により、定款で定めれば譲渡承認機関を株主総会とすることも可能です。
実際、取締役会を設置していない非公開会社では自動的に株主総会が承認機関となりますし、設置会社でも定款変更により「株主総会で承認する」方式を採用することがあります。
しかし承認機関を株主総会とする方式には、いくつか留意すべき問題点があります。
迅速性の問題
株主総会は招集通知に原則2週間前の発出が必要(会社法299条)であり、たとえ臨時株主総会であっても法定の手続きを経る必要があります。
譲渡承認請求から2週間以内に結論を出す必要がある中で、株主総会開催を要するとなれば、実質的には請求から即座に全株主に招集通知を出し臨時総会を開催するという非常にタイトなスケジュールを強いられます。
少数の株主しかいない同族会社等では、株主全員の同意による書面決議(会社法319条)で代替することも可能ですが、これも全員の迅速な署名が必要となり手間です。
取締役会決議で済む場合と比べ、物理的な時間制約が厳しい点はデメリットと言えます。
情報露出と波及効果の問題
株主総会で承認可否を諮る場合、全株主に対し譲渡希望者と譲受希望者の存在を知らせることになります。
結果、不承認として会社買い取りの決議をする際には他の株主にもその事実が伝わり、場合によっては「自分も会社に株式を買い取ってほしい」と考える株主が現れるリスクが生じます。
実際、ある会社で株主総会決議により自己株買いを決め一人の少数株主の株を買い取ったところ、他の少数株主から「自分にも同等の機会を与えよ」と追加の買取請求(これは法的拘束力のある請求ではなく任意交渉の申し入れでしたが)がなされ、経営陣が難渋した例があります。
株主総会方式は、このように社内外への情報開示が大きいため、波風が立ちやすい側面があるのです。
議決権行使の問題
譲渡承認を求めている当の株主(譲渡人)やその譲受人候補が既存株主である場合(例:既存株主Aが自分の株を既存株主Bに売るケースなど)、その利害関係人が議決権を行使できるかという問題もあります。
本件決議は当該株主自身の地位に直接影響するため、厳密には特別利害関係として当該株主の議決権行使を制限すべきとの見解もありえます(会社法第831条の類推適用検討余地)が、明文規定はなく実務的な取り扱いは定まっていません。
このような不確定要素も含め、承認決定を株主総会に委ねるのは紛争の火種となり得ます。
以上より、定款で承認機関を株主総会と定めている会社は、上記問題点を踏まえた運用ルール(招集期間短縮のための予めの同意取り付け、買取発生時の他株主対応方針の策定等)を整備することが望ましいでしょう。
もし承認機関を変更できる状況であれば、迅速かつ社内への波及を最小限に抑えられる取締役会または代表取締役等への委譲を検討する価値があります。
おわりに
非公開会社における株式譲渡制限制度は、会社の安定経営を守る防波堤である一方、その運用を誤ると会社支配権に影響を及ぼす深刻な事態を招きかねません。
本稿で述べたように、戦後の法制度の変遷を経て現行法は相当に整備・柔軟化されていますが、それでも実務上は法定期間の短さや価格評価の難しさ、悪意ある第三者への対処といった課題が残ります。
経営者は、会社法上の規定を正しく理解するとともに、自社の定款や株主構成を再点検して、平時からトラブル予防の手を打つべきです。
特に少数株主との関係で懸念がある場合には、顧問弁護士等と連携してシミュレーションを行い、いざという時の対応策を準備しておくことが重要です。
最近の判例が示すように、株式買取業者の出現は決して他人事ではなく、多くの非上場会社が巻き込まれる可能性があります。
万一「好ましくない株主」から譲渡承認請求がなされた場合でも、法が定める厳格な手続きを踏めば会社側に防御のチャンスが与えられるのです。
逆に言えば、そのチャンスを逃したり対応を誤ると、望まぬ第三者が株主となって経営に介入したり、法外な株式買取費用を強いられる結果となりかねません。
株式譲渡制限制度を正しく理解・運用し、実効的なガバナンス体制で会社の大切な株式と経営権を守っていきましょう。
【出典・参考資料】
会社法(平成17年法律第86号)第107条、第139条、第140条、第144条、第145条、第174条等の各規定
伊藤菜々子「譲渡制限株式の譲渡手続 – 全体の流れと手続上の注意点」(BUSINESS LAWYERS,2024)
鳥飼総合法律事務所「会社法QA 第3回 株式の譲渡制限」(2015)
吉田総合法律事務所「株式買取業者からの譲渡承認請求にご注意を! – 大阪高裁令和6年7月12日判決のポイント」(2024)、他。
お困りではありませんか?