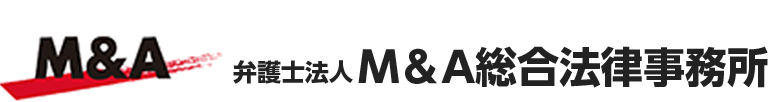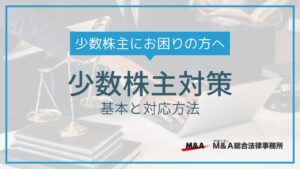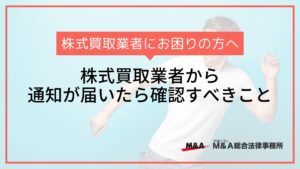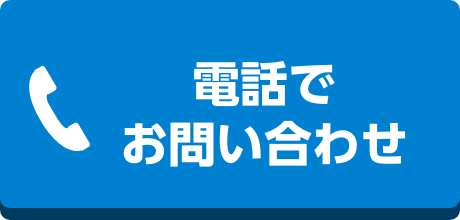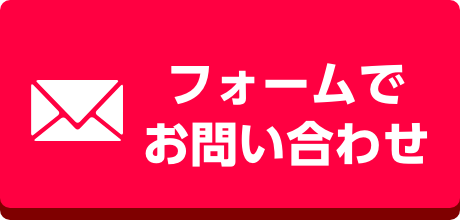スクイーズアウトとは?手法・メリットデメリット・手続きの流れを経営者向けにわかりやすく解説
お困りではありませんか?
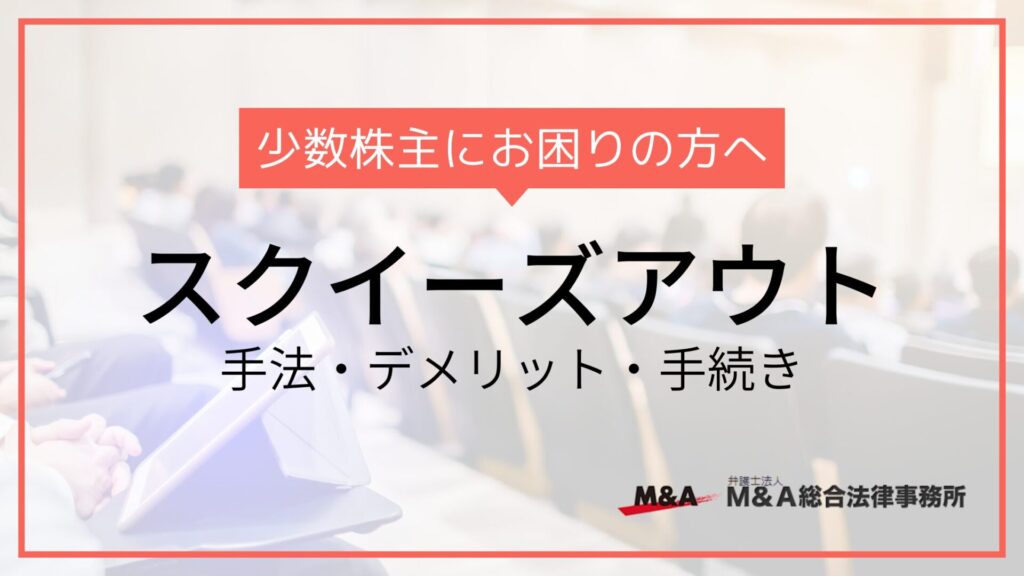
スクイーズアウトは、企業が少数株主の持株を整理して完全子会社化(議決権100%)を実現し、意思決定を素早く一元化するための代表的な手法群です。上場・非上場いずれのケースでも用いられ、特に敵対的な少数株主対応やMBO/TOB後の再編、親子上場の解消などで検討されます。
スクイーズアウトを実施する際に押さえたいのは、「どのスキームを選ぶか」によって必要要件(例:特別支配株主=議決権90%以上)や株主総会の要否、公告・備置などの手続コストと期間、さらには紛争や申立てのリスクが大きく変わる点です。
本記事では、経営者の意思決定を支える観点から、手法の違い・手続きの流れ・メリット/デメリット・実施事例までを整理して紹介します。
主な内容は次の通りです。
- 4つの手法の使い分けを比較表で解説(株式等売渡請求/株式併合/株式交換/全部取得条項付種類株式)
- 経営者視点でのメリット・デメリットと、デメリットを抑えるチェックリスト
- 迷いがちな手続きの流れ(タイムライン)とトラブル時の分岐
- 価格の相当性担保(第三者算定・公正手続)と情報開示・社内外対応の要点
- 公知情報に基づく実施事例の型整理と、学びの抽出
注意:本記事は一般的な解説です。個別の結論は保有比率・定款・過去の議事録・事業状況等により異なります。具体の適用や価格・税務の判断は、専門家にご相談ください。
スクイーズアウトとは
スクイーズアウトは、少数株主の持株を整理して議決権を100%に集約するための制度群の総称です。
スクイーズアウトを行う場合は、会社法に基づく複数のスキームを状況に応じて選択します。典型例は、特別支配株主による株式等売渡請求、株式併合、株式交換の応用、全部取得条項付種類株式です。目的は意思決定の迅速化、グループ再編、上場廃止を含む非公開化、紛争予防にあります。
主要な要件は議決権比率や決議の種類、公告や書類備置き、効力発生日の設計で、90%未満の場合はTOBや段階取得を含む選択肢の検討が必要です。価格の相当性と手続の公正確保は、価格決定の申立て等のリスク管理に直結します。
スクイーズアウトの用語定義
スクイーズアウトとは、少数株主の持株を法的手続で取得し、完全子会社化を実現する一連の枠組みを指します。代表的手法は四つです。第一に、特別支配株主の株式等売渡請求です。第二に、一定比率での株式併合です。第三に、株式交換の応用です。第四に、全部取得条項付種類株式の取得条項行使です。これらは要件、決議レベル、公告や備置き、対価の交付方法がそれぞれ異なります。
スクイーズアウトの目的
少数株主の反対や情報拡散で経営が停滞する状況では、意思決定の一元化が必要です。スクイーズアウトは、取締役会レベルの機動性を高め、長期投資や再編を実行しやすくします。
少数株主が一定の議決権割合を保有していると、会社法上の少数株主権を行使できます。例えば、議決権の3%以上で会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条)や株主総会の招集請求(会社法第297条)を行える場合があります。
議決権の10%以上では、やむを得ない事由があるときに会社解散の訴え(会社法第833条)を提起できることがあります。これらは適法な権利行使として認められ得る一方、対立があると資料開示や総会対応が反復し、意思決定や情報管理に負担が生じやすくなります。
上場会社ではTOB後の非公開化、親子上場の解消、MBO後の整理などで活用されます。
非上場会社では、対立株主による議事妨げや情報流出を抑制する狙いがあります。これらの場面で、事務コストの削減と説明責任の明確化も副次的効果として期待できます。
特別支配株主の要件
スクイーズアウトで利用可能な制度が変わるため比率の把握が最優先です。株式等売渡請求は、一般に議決権の90%以上を保有する特別支配株主が前提です。90%以上であれば、株主総会決議の負担が相対的に軽い制度を選びやすくなります。90%未満では、公開買付けや相対取得での段階取得、株式併合等の別スキームを検討します。いずれの制度でも、公告、書面の備置き、効力発生日、対価の交付時期の設計が必要です。
典型的な適用場面
グループ再編での子会社完全化が典型です。親子上場の解消や、DX投資を前提とする機敏な意思決定を求める場面で用いられます。
上場会社では、TOBで大半の株式を取得した後に、スクイーズアウトで持株比率を100%にする流れが一般的です。
非上場会社では、業績改善や事業承継に伴う株主整理で活用されます。いずれの事案でも、社内体制、情報管理、取引先や従業員への説明計画が必要です。
スクイーズアウトとTOBの違い(二段階買収)
TOB(株式公開買付け)は、市場外で不特定多数の株主から株式を買い集める方法です。
株主は提示された買付価格で売却するかどうかを自分で判断します。そのため、TOBを実施しても応募が想定より少なければ、持株比率が100%に到達しないことがあります。
スクイーズアウトは、会社法の手続に基づき、残った少数株主の株式を取得して持株比率を100%に集約する方法です。
上場会社では、まずTOBで大半を取得し、その後にスクイーズアウトで完全子会社化する流れが多く、この組み合わせは二段階買収と呼ばれます。
二段階買収では、TOB価格との整合が取れているか、取得対価の根拠を説明できるか、手続の公正性が確保されているかが、後日の価格争いを抑えるうえで重要になります。
スクイーズアウトのよくある誤解
よくある誤解として、価格は会社が恣意的に決められるという誤解がありますが、独立第三者の評価書や比較可能取引の検討等で相当性を裏付けます。
また、手法はどれも同じという理解も誤りで、必要決議・所要期間・端株処理・価格決定の申立てリスクが異なります。90%到達で自動的に実施できるわけでもありません。議事録や説明資料の整備、利益相反管理、内部統制の設計が不可欠です。
最後に税務についても一律ではありません。譲渡所得とみなし配当の区分や源泉の要否は、対価設計や株主属性によって異なります。
スクイーズアウトの4つの手法と使い分け
スクイーズアウトには複数の法的手法があり、それぞれに要件・決議水準・所要期間・リスクが異なります。選択を誤ると、手続のやり直しや訴訟リスクの拡大につながるため、目的と自社の議決権構成に応じた手法選定が重要です。
以下では、代表的な4手法を比較し、使い分け方を解説します。
株式等売渡請求(特別支配株主制度)
株式等売渡請求は、会社法第179条に基づく制度で、議決権の90%以上を保有する「特別支配株主」が、残りの株式の取得を請求できる仕組みです。
対象会社はこれに応じる義務を負い、株主総会を経ることなく株式の移転が成立します。
対象会社の承認は、取締役会設置会社であれば取締役会決議により行い、取締役会非設置会社では取締役の過半数の同意で足ります。承認後は、会社から売渡株主等へ取得日の20日前までに通知し、取得日に株式が当然に移転します。
この制度の利点は、スピードと確実性にあります。必要な議決権比率をすでに満たしていれば、最も簡潔に少数株主を整理できます。一方で、対価の算定が不当と判断されれば、少数株主から価格決定の申立てを受ける可能性があるため、第三者機関の算定書を取得し、価格の合理性を担保することが不可欠です。
上場会社のTOB完了後の完全子会社化や、非上場会社での90%超支配時に多く利用されています。
株式併合
株式併合とは、発行済株式数を減少させることで、端数となる株主を排除する方法です。たとえば「10株を1株に併合する」と定め、1株未満の端数株を現金で買い取ります。
この手法は議決権比率が90%未満のときにも利用できますが、株主総会の特別決議(3分の2以上の賛成)が必要です。賛成株主が3分の2を下回る場合や、反対株主の影響が強い場合には成立が難しくなります。
また、併合比率や買取価格をめぐって紛争化する事例もあるため、併合目的や算定根拠を議事録・通知文で明確に示すことが重要です。上場会社では比較的多く採用されていますが、非上場会社では少数株主との関係性に応じて慎重に検討する必要があります。
株式交換(応用)
株式交換とは、会社が他の会社の株式を取得し、代わりに自社株を交付する制度です。通常はグループ再編に用いられますが、スクイーズアウトの目的で金銭交付を伴う株式交換を応用するケースがあります。
株式交換契約の締結、取締役会決議、株主総会決議、債権者保護手続、効力発生の登記など、段階的な手続が必要です。対価の交付を金銭とする場合は、組織再編税制の適用可否を慎重に確認する必要があります。
この方法は、親会社と子会社の間でグループ内再編を行う際に柔軟性が高く、税務・会計上の整理を同時に進めやすい点が利点です。
全部取得条項付種類株式
全部取得条項付種類株式とは、会社が発行する株式のうち、特定の種類株式に「すべてを取得できる権利」を付与する制度です。
この制度を用いることで、普通株主の議決に基づき、会社が特定の株式を一括で取得し、対価を交付することが可能になります。
株主総会の特別決議が必要であるため、他の手法と比べて手続き負担は大きいですが、支配比率が90%に満たない場合でも利用できる点が特徴です。
また、取得する株式と引き換えに交付する対価を柔軟に設計できるため、グループ内再編や持株会社化の局面で選択されることがあります。
この制度では、事前の公告や書類備置き、株主への通知が義務付けられており、手続の透明性を確保することが重要です。
スクイーズアウトの4手法の比較表
| 手法 | 議決権要件 | 株主総会の要否 | 主な書類・公告 | 所要期間(目安) | 主なリスク | 向いているケース |
| 株式等売渡請求 | 90%以上 | 不要 | 通知・公告・備置き | 約1〜2か月 | 価格決定申立て | すでに90%超保有している場合 |
| 株式併合 | 約3分の2以上の賛成 | 必要 | 株主総会招集通知・公告 | 約2〜3か月 | 株主反対・訴訟リスク | 90%未満で整理したい場合 |
| 株式交換 | 双方の株主総会決議 | 必要 | 契約書・登記・公告 | 約3〜4か月 | 契約締結・税務調整 | グループ再編・M&A後統合 |
| 全部取得条項付種類株式 | 種類株主総会特別決議 | 必要 | 書類備置き・公告・通知 | 約2〜3か月 | 手続負担・税務判断 | グループ再編や非上場整理 |
スクイーズアウトの手法選択のポイント
1.目的を明確にすること
上場廃止、親子上場解消、対立株主排除など、目的によって最適な手法は異なります。
2.支配比率を正確に把握すること
90%の有無が、利用可能な制度を左右します。
3.価格の相当性を担保すること
第三者算定書や独立取締役の関与を通じて、公正なプロセスを整備します。
4.訴訟・申立てリスクを想定すること
反対株主が存在する場合、説明資料や議事録の整備が不可欠です。
5.税務とスケジュールを同時に設計すること
金銭交付や株式交換を行う場合、組織再編税制や申告スケジュールを確認する必要があります。
スクイーズアウトのメリット・デメリット
スクイーズアウトは、経営権の安定化や組織再編を目的として有効な手続ですが、経営者側にとっても慎重な判断が求められる制度です。ここでは、経営者視点でのメリットとデメリットを整理し、さらにデメリットを抑制するための留意点を解説します。
スクイーズアウトのメリット
1. 意思決定を迅速に行える
少数株主が存在する状態では、株主総会や取締役会での意思決定に時間がかかる傾向があります。
スクイーズアウトによって議決権を100%集約することで、経営方針の決定や資本政策の実行を迅速に行うことが可能になります。上場企業では、完全子会社化後にグループ戦略を機動的に進められる点が大きな利点です。
2. 事務負担やコストを削減できる
株主総会の開催通知、配当計算、株主名簿管理など、少数株主が存在することで発生する事務コストを削減できます。特に非上場企業では、株主ごとの意見調整や説明対応の負担が軽減され、管理コストの削減につながります。
3. 経営リスクを低減できる
少数株主の中には、経営方針に反対したり、情報開示を求めたりするケースがあります。
スクイーズアウトを実施することで、機密情報の漏えいや、対立による経営停滞のリスクを回避できます。また、意思決定を社内で完結できるため、長期的な経営戦略の実行にも適しています。
4. 税務・会計面での一貫性を確保できる
完全子会社化によって、親会社の連結会計処理が簡素化され、グループ全体での税務・会計処理の整合性を保ちやすくなります。さらに、組織再編税制を適用できる場合は、課税の繰延効果が得られる場合もあります。
5. 将来の紛争リスクを抑制できる
少数株主が存在し続ける場合、配当や経営判断を巡る紛争が発生する可能性があります(株主代表訴訟・価格決定の申立て・差止仮処分等など)。スクイーズアウトによって株主構成を整理しておくことで、将来的な訴訟や株主代表訴訟のリスクを減らすことができます。
スクイーズアウトのデメリット
1. 手続に時間とコストがかかる
手法によっては株主総会決議、公告、備置き書類の作成など、多段階の手続が必要です。特に株式併合や全部取得条項付種類株式を採用する場合は、書面整備や関係者調整に時間がかかります。これらの準備を怠ると、効力発生までの期間が延びるおそれがあります。
2. 対価の支払い負担が大きい場合がある
スクイーズアウトの実施に際しては、少数株主に対して公正な価格で対価を支払う必要があります。取得対象株主数が多い場合や、株価水準が高い企業では、支払い総額が多額となることがあります。資金調達の計画を事前に立てることが重要です。
3. 価格を巡る紛争が発生する可能性がある
対価の妥当性に不満を持つ株主から、「価格決定の申立て」が行われる場合があります。申立てが認められた場合、追加の支払いが生じる可能性もあるため、初期段階から独立第三者による評価書を取得し、価格相当性を確保することが求められます。
4. 時間的な制約と開示リスクがある
上場企業では、適時開示や公告を通じて市場に情報を発信する義務があり、スケジュール管理を誤ると市場の混乱を招く可能性があります。非上場企業でも、社内外への説明が不十分であると、従業員や取引先との関係に影響を及ぼすおそれがあります。
5. 評判・レピュテーションへの影響
スクイーズアウトは、少数株主の権利を制限する性質を持つため、実施の仕方によっては「一方的」と見られることがあります。経営者としては、公正な手続を経て透明性の高い対応を行うことが求められます。
デメリットを抑えるための留意点
スクイーズアウトの実施にあたっては、以下の点を整備することでリスクを軽減できます。
・第三者算定書の取得
価格の相当性を担保するため、独立した外部評価機関から算定書を取得します。
・手続の公正性確保
社外取締役や監査役を関与させ、利益相反を防止します。
・説明責任を果たす文書化
議事録や説明資料を作成し、判断過程を明確化します。
・スケジュールの事前設計
公告・備置き・決議・入金などの工程を可視化し、効率的に進行させます。
・外部専門家との連携
弁護士・会計士・税理士などの専門家と連携し、法務・税務・開示の観点から整合性を確保します。
スクイーズアウトの手続きの流れ
スクイーズアウトの実施には、法令に基づく段階的な手続きが必要です。手続の不備は効力発生の遅延や、少数株主からの異議・訴訟につながるおそれがあるため、事前準備と進行管理が重要です。
ここでは、一般的な流れと、各手法に共通するチェックポイントを整理します。
事前準備
スクイーズアウトを行う前に、以下の項目を確認しておく必要があります。
- 議決権保有比率の確認
議決権の90%を超えるかどうかを明確にします。この比率によって採用可能な手法(株式等売渡請求・株式併合など)が変わります。 - 定款および過去議事録の確認
定款に特別条項や制限がないか、過去に株主構成や議決権の変更がなかったかを確認します。 - 第三者算定書・社外関与の準備
価格の相当性を確保するため、独立した外部評価機関の算定書を取得します。また、売渡請求では事前備置き(179条の5)・事後備置き(179条の10)の対象書類(算定書・議事録等)を明示して整備します。 - スケジュールの策定
公告期間、株主総会、備置き書類、効力発生日、入金時期などの工程を明確にし、余裕を持って計画します。 - 社内・社外への説明準備
従業員・取引先・メディアへの説明内容を整理し、情報開示と機密保持のバランスをとる必要があります。
一般的なスクイーズアウトの手続きの流れ
スクイーズアウトは手法によって詳細が異なりますが、一般的な流れは次のとおりです。
- 取締役会による方針決定
実施の目的・手法・予定日程・算定機関の選定を決議します。 - 株主等への通知・公告
法令に基づき、株主に対して手続開始を通知します。 - 書類の備置き
会社法上、定められた期間、関係書類(契約書・算定書・議事録等)を本店および支店で備え置きます。 - 株主総会(該当する場合)
株式併合・全部取得条項付種類株式などでは特別決議が必要です。株式等売渡請求の場合は株主総会を要しません。 - 効力発生日
公告期間経過後、株式の移転や消却が効力を発します。効力発生日を基準に対価の支払いや登記を行います。 - 対価の支払い・入金処理
株主ごとの対価(現金・株式・その他)を支払い、領収・入金を完了させます。 - 事後の書類備置き・報告
実施後、会社は一定期間、関係書類を備置き、株主の閲覧に供します。
スクイーズアウトの手法別の主な工程
| 手法 | 主な工程 | 特徴 |
| 株式等売渡請求 | 特別支配株主による請求→対象会社取締役会決議→通知・公告→事前備置き→効力発生→事後備置き | 株主総会不要。最も簡潔だが、90%以上保有が前提。取締役会等の承認(179条の3)を経て、会社から取得日の20日前までに通知(179条の4)、取得日に当然取得(179条の9)となる。 |
| 株式併合 | 取締役会決議 → 株主総会特別決議 → 公告 → 効力発生・入金 | 少数株主の反対で成立困難になる場合がある。 |
| 株式交換(応用) | 契約締結 → 取締役会決議 → 株主総会 → 登記 → 効力発生 | 契約管理と税務判断が必要。 |
| 全部取得条項付種類株式 | 取締役会決議 → 株主総会特別決議 → 書類備置き・公告 → 効力発生 | 手続が複雑。社内文書整備が重要。 |
トラブルが発生した場合の対応
スクイーズアウト実施後、少数株主から価格の不当性を理由とする「価格決定の申立て」が行われることがあります。この場合、裁判所が公正価格を決定します。対応のためには、算定書・議事録・説明資料など、判断過程を裏付ける証拠を備えておく必要があります。
また、手続中に差止仮処分が申し立てられた場合は、迅速な法的対応が求められます。特に上場会社では、適時開示義務との関係で市場の混乱を最小限に抑えるため、事前にリスクシナリオを想定しておくことが重要です。
チェックポイント
- 取締役会および株主総会の決議内容を明確に記録しているか。
- 公告・通知文面が会社法の要件を満たしているか。
- 書類の備置き期間・場所が法定要件に沿っているか。
- 効力発生日と入金日が一致しているか、または合理的な間隔を設けているか。
- 実施後に株主や関係者への報告・開示を適正に行っているか。
価格の相当性と訴訟リスク低減の設計
スクイーズアウトにおいて最も重要な論点の一つが「価格の相当性」です。少数株主に交付する対価が不当であると判断された場合、株主から「価格決定の申立て」や訴訟が提起される可能性があります。経営者は、適切な算定方法と公正な手続を備えることで、リスクを最小限に抑えることが求められます。
価格の相当性が問題となる理由
スクイーズアウトでは、少数株主が自発的に株式を売却するわけではなく、会社や特別支配株主の意思によって強制的に株式を取得します。このため、法律上は「公正な価格」での取得が前提とされます。
もし提示した価格が公正でないと判断された場合、会社法182条の5(株式併合に伴う買取価格等の決定)に基づき、裁判所に価格決定を求めることができます。
この手続に発展すると、最終的な支払い額が増加するほか、手続期間が長期化する可能性があります。
価格の相当性を確保するための対応内容
1. 独立第三者による算定書の取得
最も基本的な対応は、独立した外部評価機関による株式価値算定書を取得することです。
算定方法としては、DCF法(将来キャッシュフロー割引法)、類似会社比較法、マーケットアプローチなどが用いられます。複数の手法を組み合わせることで、価格の妥当性を客観的に裏付けることが可能です。
2. 手続の公正性を確保する体制
価格が妥当であっても、手続の透明性が確保されていない場合、株主からの不信を招くおそれがあります。
具体的には、社外取締役・監査役・特別委員会を関与させることで、利益相反を回避します。特別支配株主が親会社である場合、子会社側の独立性を担保する手続設計が必要です。
3. 議事録と説明資料の整備
算定書の内容や決議過程を、取締役会議事録や株主向け説明資料に明記します。
判断の根拠や理由を記録として残すことで、後日訴訟となった場合にも、会社側の合理的判断を証明しやすくなります。また、公告・通知文でも、算定基準日や使用した算定手法を簡潔に説明するとよいでしょう。
生じやすいトラブルと防止策
(1)価格決定申立てへの対応
申立てが行われた場合、裁判所が算定書や議事録をもとに価格の合理性を判断します。
算定書の作成過程や、経営者の判断が合理的であったことを説明できるかどうかが重要です。あらかじめ複数の算定手法を用い、外部専門家の意見を得ておくことで、裁判所が認める「相当性」を裏付けることができます。
(2)反対株主の差止請求
一部の株主が手続の瑕疵を理由に差止めを求める場合があります。
公告や備置き期間の違反、株主総会の決議手続の不備などが典型です。これを防ぐためには、法定要件の遵守と、実施スケジュールの事前精査が必要です。
(3)情報漏えいと風評リスク
上場会社では、スクイーズアウト計画の漏えいにより株価が変動するおそれがあります。
公表タイミングの管理、社内アクセス権限の制限、IR部門との連携が不可欠です。非上場会社でも、従業員や取引先への情報共有を適切な時期に行い、誤解を防ぐ必要があります。
経営者が行うべきリスク低減のための準備
- 価格算定プロセスの文書化
算定の目的、使用した手法、前提条件、結果の概要を文書で残します。 - 独立性の担保
算定機関、弁護士、監査役など、利害関係のない第三者を関与させます。 - 複数手法による裏付け
DCF法、類似会社比較法など複数のアプローチを採用し、相場の妥当性を検証します。 - 社内決裁経路の明確化
取締役会や特別委員会の承認プロセスを整理し、記録に残します。 - 説明資料の整合性
社内説明用、株主向け、監査対応用の資料で記載内容を統一します
ポイント
スクイーズアウトにおける価格の相当性は、単に数値の妥当性だけでなく、その算定過程と公正な手続の透明性によって評価されます。
経営者は、第三者算定書の取得、独立した意思決定プロセス、文書化された説明責任を徹底することで、後日の訴訟や申立てに備えることができます。
手続の設計段階から法務・会計・IR担当者を巻き込み、社内体制を整えることが、リスク低減に最も有効です。
スクイーズアウトの税務の基本線
スクイーズアウトを実施する際には、会社法上の手続だけでなく、税務上の取り扱いを正確に理解しておくことが重要です。
対価の内容や株主属性によって課税関係が異なるため、誤った処理を行うと追加課税や税務調査の対象となる可能性があります。本章では、スクイーズアウトに関連する税務上の基本的な考え方を整理します。
譲渡所得とみなし配当の区分
スクイーズアウトで株式を取得する際に支払われる対価は、原則として株主にとって譲渡所得またはみなし配当のいずれかに区分されます。
どちらに該当するかは、支払対価の性質によって判断されます。
・譲渡所得
株式等売渡請求や株式併合によって株式を譲渡したとみなされる場合に適用されます。譲渡所得は、売却価額から取得費および譲渡費用を控除して算出され、所得税・住民税が課税されます。
・みなし配当
会社が株主に対して自己株式の取得等を行う場合、その取得価額のうち資本金等の額を超える部分は、配当とみなされることがあります。配当所得として源泉徴収の対象となり、確定申告が必要となる場合もあります。
この区分は、会社側の会計処理や、対価の性質(現金・株式など)によって異なるため、実施前に税理士と協議しておくことが望ましいです。
組織再編税制との関係
スクイーズアウトの中には、組織再編税制の適用対象となる手法もあります。株式交換や全部取得条項付種類株式などのスキームでは、組織再編の一種として取り扱われ、一定の要件を満たす場合に「適格組織再編」として課税の繰延が認められます。
適格要件の主なポイント
- 対価の50%超が株式であること。
- 事業継続性要件(再編後も主要事業を継続すること)。
- 支配関係継続要件(再編前後で50%超の支配関係を維持すること)。
上記を満たさない場合は「非適格組織再編」として扱われ、資産の時価評価課税や株主側の課税が発生します。非適格と判断された場合の負担は大きいため、手法選択時点で税務上の影響を精査する必要があります。
株主側の税務上の留意点
1. 個人株主の場合
個人株主がスクイーズアウトによって株式を譲渡した場合、通常は譲渡所得課税(申告分離課税20.315%)の対象になります。
証券口座を通じて行われる取引では、特定口座内での源泉徴収により申告不要の場合もあります。一方で、非上場株式や相対取引による場合は、確定申告が必要です。
2. 法人株主の場合
法人が保有する株式を譲渡する場合、譲渡益は法人税の課税対象となります。
みなし配当として処理される部分については、受取配当金の益金不算入制度の適用可否を確認します。資本剰余金を取り崩して支払う場合は、課税所得の計算上、処理を誤ると過少申告となる可能性があるため注意が必要です。
会社側の税務上の留意点
会社側では、取得した株式の対価をどの勘定科目で処理するかを検討する必要があります。
一般的には、自己株式の取得または株式交換対価の支出として処理します。また、組織再編税制上の「資産譲渡」や「事業譲渡」とみなされる場合には、時価評価課税の対象となることがあります。
上場会社の場合は、開示資料(有価証券報告書・臨時報告書)における税務処理の開示にも注意が必要です。特に税効果会計の適用範囲や、繰延税金資産の計上方法については、監査法人の確認を受けておくことが望まれます。
ポイント
スクイーズアウトの税務処理は、会社法上の手続よりも複雑な判断を要します。
譲渡所得とみなし配当の区分、組織再編税制の適用可否、株主・会社双方の課税関係を整理し、事前に専門家の確認を得ることが不可欠です。 税務の誤りは、スクイーズアウト完了後に判明することが多く、修正申告や追加課税につながるおそれがあります。
したがって、法務・税務・会計の三分野を統合して進行管理を行うことが、安全といえます。
スクイーズアウトが実施された事例
スクイーズアウトは、上場・非上場を問わず多様な目的で活用されています。
上場企業ではTOB後の完全子会社化、非上場企業では対立株主の整理や経営権の安定化を目的として行われます。ここでは、公知情報をもとに実際に実施された事例を紹介し、それぞれの手法と背景、留意点を整理します。
※以下は公知情報に基づく一般的整理となり、具体数値・日付・対価は各社の適時開示・臨時報告書・有報に従っております。
【情報通信×インターネット】ZホールディングスによるLINEの完全子会社化
目的と背景
Zホールディングス株式会社(現・LY Corporationグループ)は、グループ内の意思決定の迅速化と統合効果の最大化を目的に、LINE株式会社との統合を進めました。ソフトバンクとNAVERによる共同TOBを起点とし、持株会社体制の再編を含む一連の統合プロセスでグループ再編を完了しています。
採用した手法
本件は、共同TOBの成立を前提に、その後の組織再編(吸収合併・会社分割等)を段階的に実施する構成でした。日本では、TOB後のバックエンドとして株式併合や特別支配株主による株式等売渡請求など複数のスクイーズアウト手法が一般に用いられます。
手続と結果
2020年の共同TOB成立を経て、2023年10月1日にグループ再編手続の完了(吸収合併・会社分割等)とLY Corporationとしての新体制移行が公表されています。統合プロセスでは、適時開示や再編スキームの公告・説明が段階的に行われました。
ポイント
TOB後の完全子会社化・統合では、二段階取得スキーム(TOB→バックエンド)に合わせ、開示・手続の整合と価格相当性・公正手続の確保が重要です。再編手法が複合する場合は、効力発生日と開示時期の整合を明示し、ステークホルダーへの説明責任を徹底する必要があります。
【運輸】佐渡汽船×みちのりホールディングス
目的と背景
みちのりホールディングス株式会社は、地域交通の安定化と事業再生を目的として、佐渡汽船株式会社に出資・支援を行いました。第三者割当等により議決権多数を確保した上で、株式併合を活用して少数株主の整理と上場廃止のプロセスが進められています。
採用した手法
第三者割当による資本注入と支配確立の後、株式併合(会社法180条)を実施して少数株主を整理する構成が採られました(公告・スケジュールの事前明示あり)。
手続と結果
取引所の整理銘柄指定・最終売買日・上場廃止日・株式併合の効力発生日が順次公表され、効力発生日に少数株主整理が完了しています。上場廃止の決定は取引所からも公表されています。
ポイント
再生型M&Aでは、社会的影響の説明とともに、株式併合に伴う反対株主保護(会社法182条の4〜5)を踏まえた文書化・周知が重要です。公告文書で取得目的・算定の考え方・効力発生日を明確にし、手続の透明性を担保します。
【小売】ローソン×KDDI・三菱商事
目的と背景
KDDI株式会社および三菱商事株式会社は、コンビニエンスストア事業における経営効率化とデジタル戦略の推進を目的に、ローソン株式会社に対する公開買付け(TOB)を実施しました。完全子会社化とグループの機動性向上を狙いとしています。
採用した手法
TOBの後段手続として、株式併合によるスクイーズアウトを実施・公表(会社法180条)。当該併合に関する通知・参考資料がローソンから開示されています。
ポイント
上場廃止を伴うスクイーズアウトでは、投資家・従業員・取引先への説明責任が特に重視されます。併合比率や支払開始日等の開示整合性と、特別決議を含むコーポレート・アクションのタイムライン管理が信頼確保の要となります。
【アパレル】紳士服中西によるオンリーの完全子会社化(MBO)
目的と背景
紳士服中西株式会社は、MBO(Management Buyout)により株式会社オンリーの非公開化を進め、長期的なブランド戦略の遂行と経営の独立性確保を目的としました。TOBの開始と会社側の賛同は公表されています。
採用した手法
TOB成立後、紳士服中西が90%未満の議決権取得にとどまったため、バックエンドとして株式併合(会社法180条)を実施。臨時株主総会で特別決議を経て、1,610,806株を1株に併合するなど具体的スケジュール・内容が開示されています(整理銘柄指定→上場廃止→効力発生日)。
ポイント
MBO型のスクイーズアウトでは、価格の公正性と利益相反管理(独立委員会・第三者算定・プロセス開示)が重要です。株式併合を用いる場合、反対株主の買取請求・価格決定申立ての手当を周知し、文書化・開示を整えることが求められます。
【電機】ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア(BPEA)によるパイオニアの完全子会社化
目的と背景
ベアリング・プライベート・エクイティ・アジア(BPEA)は、経営再建を目的にパイオニア株式会社に第三者割当等で資本注入・支配権取得を行い、完全子会社化(非上場化)を進めました。
採用した手法
資本注入に続き、株式併合を用いたスクイーズアウトを行い、上場廃止(2019年3月27日)に至った旨がパイオニアから公表されています。
ポイント
PEファンドによる再建型スクイーズアウトでは、再建計画との整合性・資金繰りに加え、第三者算定書・開示の充実で価格相当性と公正手続を明確にすることが、争点(価格決定・差止)を抑制します。
スクイーズアウトの事例まとめ
| 事例 | 採用スキーム | 目的 | 所要期間(目安) |
| ZHD×LINE | TOB+組織再編(合併・会社分割等) | グループ統合・上場廃止 | 約2か月 |
| 佐渡汽船×みちのりHD | 第三者割当+株式併合 | 経営再建 | 約2〜3か月 |
| ローソン×KDDI・三菱商事 | TOB+株式併合 | 経営効率化・DX推進 | 約2か月 |
| 紳士服中西×オンリー | TOB+株式併合 | MBO・経営独立 | 約3か月 |
| BPEA×パイオニア | 第三者割当+株式併合 | 再建・非上場化 | 約2か月 |
出典:
- ZHD/LINEの統合・再編(TOB結果・再編完了)
- 佐渡汽船の第三者割当・株式併合・上場廃止
- ローソンのTOB後の株式併合方針・通知資料
- オンリーのTOB・株式併合・上場廃止スケジュール
- パイオニアの第三者割当と株式併合・上場廃止公表
ポイント
実際のスクイーズアウト事例からは、手法選択と手続設計の正確さが成功の要因であることが分かります。
特に、TOB→バックエンド(株式併合/株式等売渡請求 等)の二段階構成では、価格相当性の裏付け(第三者算定・独立委員会 等)、公告・通知・効力発生日の整合、社会的影響への配慮が重要です。各社の開示資料を踏まえ、自社の目的と状況に適したスキームを選定してください。
FAQ(よくある質問)
スクイーズアウトの実施に際しては、少数株主や経営者から多くの質問が寄せられます。ここでは、特に相談の多い質問を取り上げて解説します。
Q1. スクイーズアウト後、株は最終的にどうなりますか?
スクイーズアウトが完了すると、少数株主が保有していた株式は、効力発生日にすべて特別支配株主または会社に移転します。株主名簿からも除外されるため、少数株主の株式保有は消滅します。
その代わりに、公告または通知で定められた対価(現金や株式など)が支払われます。また、上場廃止は取引所の所定手続により行われ、スクイーズアウトの効力発生日と一致しない場合があります。
Q2. 対価の入金(現金化)はいつ行われますか?
対価の支払時期は、効力発生日から数日〜数週間以内が一般的です。会社法上は、効力発生後に「速やかに」支払うこととされていますが、入金処理や口座確認等に要する期間を考慮します。
公告や通知に記載される「支払開始日」が正式な基準日となるため、必ず確認する必要があります。また、証券会社経由で保有していた場合は、証券口座への入金となり、日数がやや前後することがあります。
Q3. 上場廃止になった株を持ち続けた場合、どうなりますか?
上場廃止後も、スクイーズアウトが効力を生じていない間は株主としての地位を持ちますが、効力発生日以降は株式が自動的に移転します。したがって、上場廃止後に株を「持ち続ける」ということはできません。
もし対価の受取り手続きを行っていない場合でも、会社側は法定の公告期間後に預り金として保管します。指定の手続を行えば、後日でも対価を受け取ることができます。
Q4. 提示された価格に不満がある場合、どうすればよいですか?
少数株主は、会社法182条の5に基づき、効力発生日から30日以内の協議が整わない場合、その満了後30日以内に裁判所へ価格決定の申立てが可能です。
株式併合:効力発生日から30日以内に協議が整わない場合、その満了後30日以内に申立て(会社法182条の5)
株式等売渡請求:会社法179条の8により、取得日の20日前から前日まで申立て可能です。
裁判所は、提出された算定書や証拠資料を基に「公正な価格」を判断します。
ただし、算定書や取締役会議事録などの客観的根拠が整備されている場合、会社側の価格がそのまま認められるケースが多いです。経営者としては、申立てリスクを見越して、算定書と議事録を適正に整備しておくことが重要です。
Q5. スクイーズアウトで得た現金は確定申告が必要ですか?
課税区分は、対価の内容や株主の属性によって異なります。
多くの場合、株式の売却と同様に譲渡所得として扱われ、確定申告が必要です。ただし、証券会社の特定口座で取引されていた株式の場合、源泉徴収で納税が完結しているケースもあります。
一方で、会社が自己株式を取得する形となった場合は、みなし配当として扱われる可能性があります。詳細は税理士等の専門家に確認することが望ましいです。
Q6. 何%の議決権を保有すればスクイーズアウトができますか?
スクイーズアウトを行うためには、議決権の90%以上を保有していることが前提となります(特別支配株主の要件)。
90%未満の場合でも、株式併合や全部取得条項付種類株式など、他の手法を用いることで少数株主を整理することが可能です。ただし、いずれの方法を採用する場合でも、手続の透明性と価格相当性の確保が求められます。
Q7. 非上場会社でもスクイーズアウトはできますか?
非上場会社でも、会社法に基づいて株式等売渡請求や株式併合の手続を行うことができます。
ただし、非上場会社では公告・開示が限定的なため、株主とのトラブルを防ぐためにも、対価算定の根拠や説明資料の整備を行うことが重要です。また、関係者(従業員・取引先)への説明を丁寧に行うことも信頼維持につながります。
Q8. スクイーズアウトの期間はどれくらいかかりますか?
手法や会社の規模によって異なりますが、一般的には2〜4か月程度が目安です。
株式等売渡請求制度を利用する場合は比較的短期間で完了しますが、株式併合や全部取得条項付種類株式を用いる場合は、株主総会の開催や公告期間を含めるため、もう少し時間を要します。実際のスケジュールは、公告期間、算定書の作成、登記手続などを含めて検討することが必要です。
スクイーズアウトの実施前に確認すべきこと
スクイーズアウトを円滑に進めるためには、実施前の準備が非常に重要です。
ここでは、経営者が確認すべき主要項目を 「法務」「財務・税務」「社内・外部対応」 の3つの観点からチェックリスト形式でまとめます。これらを事前に整備しておくことで、手続の遅延や訴訟リスクを防止し、社内外からの信頼を確保できます。
法務面のチェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
| 1. 議決権比率の把握 | 現時点での議決権保有割合を正確に算定していますか。90%以上であれば株式等売渡請求の利用が可能です。90%未満の場合は段階取得を検討します。 |
| 2. 定款・株主構成の確認 | 定款に特別条項や取得制限が存在しないか確認していますか。過去の議事録・株主名簿も最新状態に保たれていますか。 |
| 3. 手法選定の妥当性 | 株式等売渡請求・株式併合・全部取得条項付種類株式・株式交換の中から、自社の目的に合致した手法を選定していますか。 |
| 4. 公告・備置き書類の準備 | 必要書類(算定書、契約書、議事録、通知書等)を法定期間内に備置き・公告できる体制がありますか。 |
| 5. 効力発生日と支払時期の設計 | 効力発生日、入金日、登記申請日を整合的に設計していますか。法務局・金融機関との調整は完了していますか。 |
財務・税務面のチェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
| 1. 価格算定の合理性 | 外部評価機関による算定書を取得し、価格の相当性を客観的に立証できる状態ですか。 |
| 2. 資金調達計画の策定 | 少数株主に支払う対価の資金をどのように準備するか、調達手段・支払スケジュールを策定していますか。 |
| 3. 税務シミュレーションの実施 | 譲渡所得・みなし配当・組織再編税制など、各手法の税務影響を比較していますか。 |
| 4. 会計処理と開示対応 | 自己株式取得・組織再編・税効果会計など、財務諸表上の処理が監査基準に適合していますか。 |
| 5. 税務申告・源泉対応 | 株主側・会社側双方の申告手続きが確実に行われるよう準備されていますか。通知文への説明も明記されていますか。 |
社内体制・外部対応のチェックリスト
| 確認項目 | 内容 |
| 1. 社内責任者の明確化 | 手続全体を統括する責任者(法務・経営企画・総務等)が明確に設定されていますか。 |
| 2. 社外専門家の選任 | 弁護士・会計士・税理士・評価機関など、専門家チームが連携体制を構築していますか。 |
| 3. 社内周知と情報管理 | 経営陣・従業員への周知、情報漏えい防止措置(アクセス制限・文書管理等)は適切に行われていますか。 |
| 4. 取引先・金融機関への説明 | 資本構成の変化に伴う取引影響を考慮し、主要取引先・金融機関へ事前説明を行っていますか。 |
| 5. ステークホルダー対応計画 | メディア・自治体・地域社会など、外部への影響を踏まえた広報計画を策定していますか。 |
ポイント
スクイーズアウトの準備段階では、法務・財務・社内体制の三面から同時に確認を進めることが求められます。特に、議決権比率・価格算定・公告手続・税務処理は、後戻りが困難な工程です。実施前にこのチェックリストをもとに全体の整合性を確認し、関係者間での情報共有を徹底することが、手続の安全かつ円滑な遂行につながります。
少数株主にお困りならご相談ください
スクイーズアウトは、単なる株式の整理手続ではなく、経営の安定化と企業価値維持を目的とする経営判断です。
スクイーズアウトの実施を検討する際、経営者の置かれた状況によって、最適な法的手続や進め方は異なります。弁護士法人M&A総合法律事務所では、敵対的な少数株主の対応に悩む経営者の方々を対象に、初回の法的整理から実行支援まで一貫してサポートしています。
弁護士法人M&A総合法律事務所
https://www.squeezeout.jp/squeezeout/
電話でのご相談予約も可能です。
(※通話は秘密厳守・全国対応)
- 「少数株主が経営情報の開示を求めている」
- 「過去の取締役選任議決に反対する株主がいる」
- 「TOB後の完全子会社化を最短で行いたい」
- 「価格決定申立ての対応を専門家に任せたい」
- 「スクイーズアウトを検討しているが、費用と期間を知りたい」
当事務所が最適な解決策を提示します。 まずはご相談ください。
お困りではありませんか?